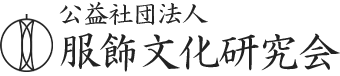愛しの銘仙(会報34号より)
今回は会報34号(平成13年12月)トップページの渡邉名誉会長のエッセイをお届けします。
銘仙といえば、私にも遠いなつかしい想い出がある。
小学校二年生のとき授業参観に母ではなく、どうしても若く美しい兄嫁に来てほしいと駄々をこねて家の者たちを困らせた。色白の兄嫁は、青紫地に大きな花柄の銘仙に、鴇色の染帯を締めて教室の後ろの隅の方に立っていた。友達の、どのお母さんよりもきれいなのが嬉しくて兄嫁の手をしっかりと握って、学校の中を案内し、だれかれとなく髭の校長先生にまで得意気に紹介して、末っ子のみそっかすの私は後々まで家中の笑い者になったのだった。 三年後の昭和十六年、大東亜戦争が始まり、やがて兄達二人も兵役にとられた。
ある日、学校から帰るとひっそりとした家のなかで、兄嫁が赤ん坊をあやしながら縫いものをしていた。それは、あの想い出の銘仙で国民服(モンペの上下)に作り替えているのだった。淋し気な兄嫁の横顔が何故か可哀想な気がして、私はむずがる赤ん坊をおんぶして軍歌を歌いながら、庭の中を歩きまわった。知らぬ間に眠ってしまった赤ん坊の重さが肩にくい込み、キリキリと頭の芯まで痛くなったことを覚えている。
両親の3回忌も終え、一人の姉も結婚してさらに淋しくなった昭和二十三年の晩秋、兄嫁が、「あんまり可愛い柄だったので。チーちゃんも来年は十九の厄だし」などと、兄に半ば言い訳をしながら銘仙の反物を広げた。ローズ色の地に大小の追い羽根が飛んでいる柄であった。はたして私の十九の初春は、兄嫁の心尽くしの晴着を着て、欠けるところが無い程の丸い顔をして写真に納まっていた。
今、五十代以上の人なら大概は銘仙を知っていると思うし、六十代以上の人であれば男女を問わず、銘仙とのかかわりで過ぎた日の哀歓、また人生の機微について物語る想い出の一つや二つはあると思う。
何故なら銘仙は、明治の中頃から大正、昭和と約百年間あらゆる階層の女性が外出着から平常着まで、それぞれの階層に応じて着られたからである。つまり生活に密着していたのであった。
それ程までに愛好された理由は、第一に絹であるから軽い上に光沢が美しい。第二はドイツ染料を使うようになって、美しい色合いと解(ほぐし)捺染など高度な手間のかかる染色法を駆使して、大胆で華やか、モダンで面白い柄を生み、他の先染織物には見られない表現の自由さがある。そして第三は鉄製力織機の導入による量産で、比較的安価であったなどと考えられる。
庶民に絹を着せ、衣生活を彩った銘仙、隆盛をきわめ一時代を築いた銘仙の産業は、昭和四十年代にその火が消えてしまった。
先日、調査研究室員と秩父を訪れた折、銘仙研究会の方々のお話をうかがう機会に恵まれ、現在銘仙の再生にかけて努力しておられるとの事、実現される事を祈念して止まない。
※鴇色 薄紅色、うすもも色